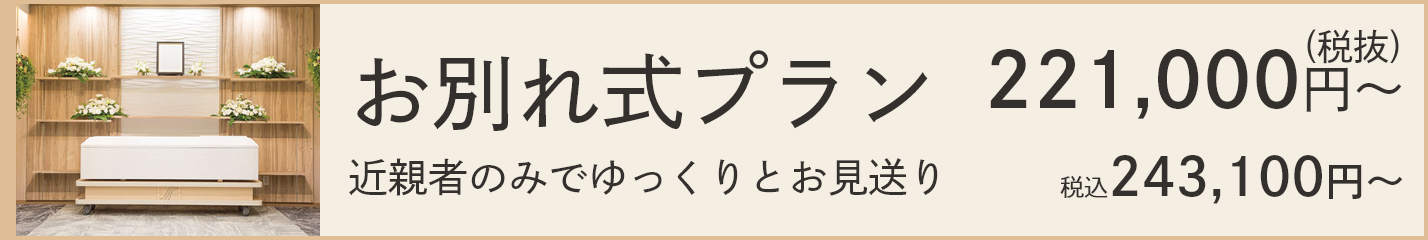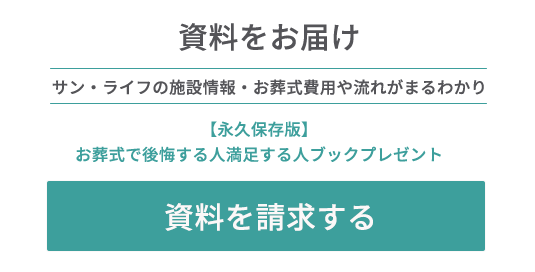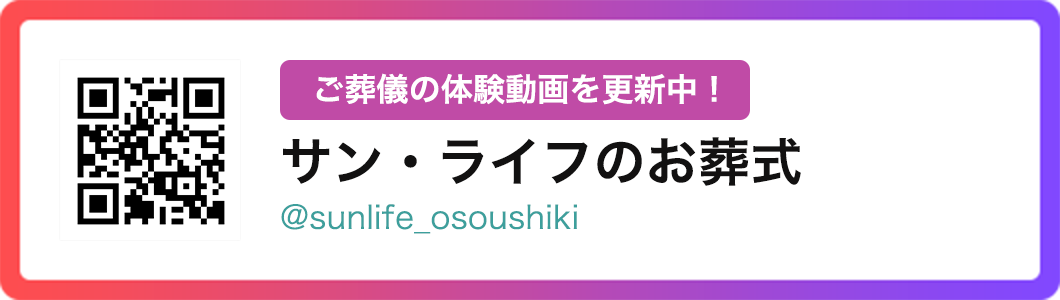遺影となった写真は、夫と北京へ旅した時のものを選んだ。
最後となったその写真を見るたび、その日の行程や食事、好きだったビールの味が思い出される。
定年後、二人で旅し、これからはゆっくり計画立てて老後を静かに暮らそうと楽しみにしていた。
北京から帰って一週間後。ことのほか残暑厳しい九月の日に、夫は崩れるように倒れた。
呼びかけにも応えない夫の異変に、救急車を頼み病院へ運んでもらったが、ICUに入った夫との面会はほんの十分程。
呼びかけて手を握ると、その日は握り返してくれた。娘は喜んで「お父さんが、お父さんが力入れて応えてくれてるよ」と興奮気味。私も手を握りしめ心を通わせようと努めたが、次の日にはもう反応がなく、そのまま声を発することもなく永遠の眠りについた。穏やかな優しい顔には、目尻から泪が流れ、残された私達家族を号泣させた。
定年したばかりの歳であった。家族の為に働き通した一生、やっとこれからという矢先の出来事であった。神も仏も無情だと、悲しみは恨みに変わる。
上の空で葬儀を進める中、「故人の好きだった曲を流しましょう」と言われ、車通勤の夫がいつも好きで聴いていたジャズが頭に浮かぶ。彼と私の青春時代そのものである。
葬儀にジャズはどう考えても合わないと思いつつも恐る恐るその事を話してみると、担当の方は快く「それは故人に何よりの送葬です。好きな曲に送られて、きっと喜ばれますよ」と言って頂き、嬉しく思いお願いした。
子や孫の手紙、思い出の品を入れ、好きだったゴルフスタイルで棺に横たわる夫は、今にも起きてきそうである。耳は胎内で一番に母の声を聴き、命終えても聴こえており、通夜のお経はそれが故に上げるという。
葬儀には不似合いだったが、ビング・クロスビーやルイ・アームストロングに送られて、夫にはこの上ない別れの曲に聴こえたであろう。私は夫があの曲を聴いていたと信じている。
サン・ライフの方の寛大なお心に感謝です。